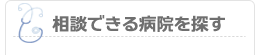治療に使用する2種類の外用薬 4
[これが基本となる正しい治療です] 古江増隆 九州大学大学院皮膚科学教授
2014年9月04日 [木]
おすすめアトピー記事
環境の改善は、ダニの除去や食べ物の制限ではありません
「環境」という言葉について、勘違いされやすいのでひとことつけ加えておきましょう。患者さんに「環境を改善するように」と指導すると、一生懸命に掃除機をかけて徹底的にダニを除去したり、食べ物の制限ばかりに気を配ったりする人が少なくありません。どうやら環境とアレルゲン(アレルギー症状をおこす原因物質)を混同しているようです。医師が意図する環境とは、「規則正しい生活を送る」、「汗対策をしっかりする」、「ストレスをためない」といった、日常生活の基本的な改善を指します。
アトピー性皮膚炎は、季節や生活環境、ストレスなどによって症状が左右されやすい病気です。医師の指示どおりにしっかりと治療していても、不規則な生活やストレスがかかる環境に身を置いていれば、治療効果は思うように上がりません。ですから、食生活が不規則なら1日3食の時刻を決めて、栄養のバランスのとれた食事をする。また、睡眠はしっかりとる。汗をかいたらタオルでふき取るか、衣類をこまめに着替える。ストレスはためないなどに気をつけ、症状を悪化させる条件にはしっかり対策をとるようにしましょう。
では、次に、具体的な治療の進め方について2歳未満、2歳から12歳未満、13歳以上の年齢別に解説していきたいと思います。

(正しい治療がわかる本 アトピー性皮膚炎 平成20年10月30日初版発行)
古江増隆 九州大学大学院皮膚科学教授
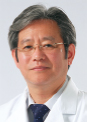
85年同病院皮膚科医局長。
86年、アメリカのNational Institutes of Healthの皮膚科部門に留学、88年東京大学医学部附属病院皮膚科復職。
同年東京大学皮膚科学教室講師、病棟医長。
92年山梨医科大学皮膚科学教室助教授、95年東京大学医学部皮膚科助教授。
97年九州大学医学部皮膚科教授、2002~04年九州大学医学部附属病院副院長兼任。
08年より九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センターセンター長兼任。
02~04年厚生労働省研究班「アトピー性皮膚炎の既存治療法のEBMによる評価と有用な治療法の普及」主任研究者、05~08年同「アトピー性皮膚炎の症状の制御および治療法の普及に関する研究」主任研究者。